函館・道南では、地元の資源やオリジナルな技術を活用したユニークな企業が数多く活躍しています。
当ホームページでは、それらの企業を取材し、広く全国に向けて発信しています。
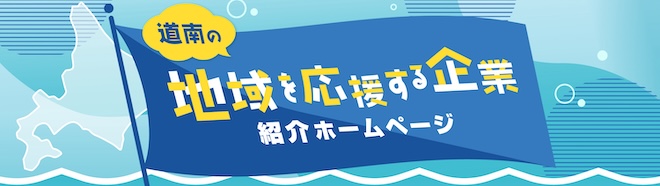
|

|

 かつて函館の花形産業のひとつだった造船業。タンカーに代表される大型船から、イカ釣り船のような中・小型の漁船まで、たくさんの船が次々と竣工していった。そんな時代に、地元の造船会社の下請として、おもに配電盤などの製作をおこなう東和電機製作所が創業された。昭和38年(1963年)のことである。
↑会長 浜出 雄一さん
飛躍のきっかけは、ユーザーからの要望だった。先代社長の親戚である松前の方から、手巻式のイカ釣り機の製作を依頼されたことがきっかけとなって、電気式自動イカ釣り機の開発が始まった。
「はまで式自動イカ釣り機」と命名された商品は、昭和44年(1969年)に販売が開始されると、その4年後には年間1万台を越す大ヒット商品に成長した。ところが、他の大手機械メーカー等がこぞって市場に参入し、同社は「イカ釣り機」製造のトップシェアの座を奪われることになる。
しかし、同社によるイカ釣り機(ロボット)の開発は、イカ漁をはじめとする漁業技術における新たな時代を切り開くものだったのは確かだ。
同社は、昭和59年(1984年)に販売開始したコンピュータ式イカ釣りロボットで再度トップに返り咲く。
最盛期には全国で40社以上の企業が、イカ釣り機の製造をおこなっていた。しかし、現在まで残っている企業は同社を含め2社しかない。
|
| 創立 |
1963年12月 |
| 代表者 |
代表取締役 浜出 滋人 |
| 住所 |
〒040-0077
函館市吉川町6-29
|
| TEL |
(0138)41-4410 |
| FAX |
(0138)41-2867 |
| URL |
http://www.towa-denki.co.jp/ |
| 従業員 |
50名 |
| 年商 |
30億円 |
| 資本金 |
9,900万円 |
|
| |
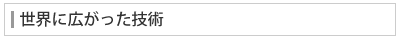
東和電機製作所が、いまだイカ釣り機のトップメーカーである理由は、始めの一歩を踏み出した以降も、次々と新しい製品の開発に取り組んできたことにある。
そのひとつがコンピュータによる中央制御の採用である。それまで、複数の釣り針を機械的に同じタイミングで海中へ投入していたものが、ブリッジ(操舵室)のコンピュータにより複数の釣り針を個別のタイミングで海中で上下させることが可能になった。
この釣り針の動きは「シャクリ」と呼ばれる運動で、イカ釣り漁師たちが長年の経験から体得する技術だった。その技術を数値化してプログラムすることに成功したのである。
この技術革新をきっかけに、同社製品のシェアは世界規模となり、中国・韓国・台湾などの東南アジア、アルゼンチン、ニュージーランドなど世界30カ国へ拡大した。
|
![自動イカ釣り機[EX-1]](images/enterprise/touwa/touwa_ika1.png)
▲自動イカ釣り機[ EX-1 ]

▲イカ釣り機の操作パネル
|
| |
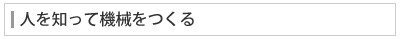
「私たちは機械屋というより、お客様のお悩み相談室なんですよ。」
イカ釣り機の開発現場にも携わった会長・浜出雄一さんは、同社の理念をこう説明した。
「人間の動き。つまり、イカ釣り名人たちが操る針の動きを、どうしたら再現できるか。その試行錯誤がマイコン(コンピュータ)の採用につながったわけです。お客様に新しい機械を持ち込みます。ところが、まずは突き返されるわけです。『こんなもの使い物にならない…』と怒られる。そこで再度工夫を重ねていくわけです。そういうプロセスを経て、やっとお客様の満足が得られるわけです。」
近年、全国的な知名度を得た津軽海峡のマグロ漁船のほとんどに、東和電機製作所製の一本釣り機が搭載されている。
「ひとりの名人がファンになってくれると、周りの漁師たちが『あの名人の使っている機械なら俺も使いたい』という感じで広がっていくんです。」
その信頼を勝ち取るためには、とことんまで現場に通いつめ、ユーザー(漁師)の意見や要望をくみ取り、確実に実現させなくてはならない。しかも、それは名人のもとでおこなわなければ意味がない。機械づくりは、人間を知ることから始まるのだという。
「海の人たちからいただいた言葉は、私たちの企業の原点です。」
|

![一本釣り機器[MR-400]](images/enterprise/touwa/touwa_ika3.png)
▲一本釣り機器[ MR-400 ]
|
| |
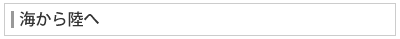
イカ釣り漁船の内部のような厳しい環境のもとで、コンピュータの搭載を実現した技術力は、現在の製品開発にも生かされている。
「これまで私たちがつくってきたのは、漁具としての機械ですから、必然的に厳しい環境に耐えうるものを開発してきました。そのノウハウを生かして、厳しい気象条件や環境にも適応できる製品を提案しています。」
そのひとつはLEDを採用した電灯(街路灯など)だ。すでに、イカ漁やサンマ漁の漁船で使う集魚灯として、LED照明を実用化している。消費電力は白熱電球の10分の1、ハロゲンライトや白熱灯に比べて長寿命、さらに輝度が高いという特徴も兼ね備えている。紫外線が少なく目に優しいので、物が見やすいといったメリットもある。
海から陸へ。新たな展開が始まっている。
|

▲実際に漁で使用されているサンマ釣り用のLED照明
|
|
| |
